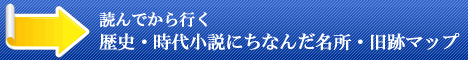「—–随分と減ったものだ。」
吉良邸討ち入り前夜、首謀者の大石内蔵助は脱落者が続出した組の再編成に腐心していた。最後に残った浪士は四十七人。うち、戦力と成り得るのは30人程だった。そして吉良邸を守る相手の数は屈強の百余名だ。
大石内蔵助は敵方に対し巧みに謀略を仕掛け続けたが、実際に討ち入りが始まるのは残りの80ページあたりからだ。そこに至るまでの諜報戦が本書の大半を占める。
内蔵助に対するは敵方の色部又四郎。討ち入りの危機を感じ取った色部だったが、念入りな作戦をじっくりと展開して行く内蔵助に対し、色部にはどこか焦燥感が付きまとっていた。色部に肩入れして本書を読み進めて行くと疲労を伴った緊張感に包まれる。
赤穂浪士の中でもスター性を感じさせる剣客堀部安兵衛よりも、ある種のカリスマ性を世に示す大石内蔵助よりも、彼らの謀略にどこまでも食らいついていく色部の存在こそが、この小説を面白くする最大の要素だったと言えよう。
本書では赤穂浪士が討入りに至るまでの様々な動機が見受けられるが、決行に至った時の心境は以下の詩に集約されている。
「かくすれば かくなるものと しりながら やむにやまれぬ 大和魂」
幕末の思想家・吉田松陰が彼らに手向けて詠んだ歌だ。
読了: 2005年3月

![]() 写真は港区泉岳寺の大石内蔵助像
写真は港区泉岳寺の大石内蔵助像

![]() 同境内、四十七士墓所の門
同境内、四十七士墓所の門