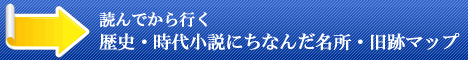「燃えよ剣」、「黒龍の柩」、幕末の新撰組を描いた小説の主人公はいずれも土方歳三だった。しかし、本書の主人公は新撰組局長・近藤勇だ。局長、とは後の肩書きだが、新撰組結成以前は剣術道場・試衛館の主だった。
門弟たちに慕われていたのだろうか、永倉、沖田、土方などが近藤に接する言葉や思いには屈託がなく、また深い親しみを感じる。近藤は朧気ながらも志を立て、やがて新撰組を結成し活躍が認めらた。しかし、近藤が出世しようとも彼らの近藤に対する気持ちは変わらなかったようだ。近藤が身分相応にどれだけ威風を正そうとも、門弟たちはどこか彼を茶化してしまうのだ。その様子がどこか微笑ましい。試衛館時代の「近藤さん」のままでいて欲しかったのだろう。
同じ新撰組を描いた小説でも、前述した2作品は雰囲気が違う。主人公が違うのだから当然だろうが、土方には冷徹感と絶え間ない緊張感が漂っていた。それこそが、幕末ものを読む愉しみでもあるのだが、本書にはまた違った愉しみを求めることが出来よう。剛剣を振るう一方で見せる近藤の憎めない人柄とそれを取り巻く人々とのやり取りだ。
本書には、特に気に入ったくだりが3つある。一つは試衛館時代に助っ人剣士を呼ぶくだり、次に新撰組結成当時の芹沢一派に手を焼くくだり、そして京で活躍するくだりだ。いずれのくだりも、近藤の言動のみが魅力的であるのではなく、それよりもむしろ近藤を慕う者たちによる彼への評価こそが、本書の主人公の人柄を読む上で興味深い。
読了:2005年 8月

![]() 千葉県流山市、近藤勇陣屋跡。彼にとっては最後の陣営となった。
千葉県流山市、近藤勇陣屋跡。彼にとっては最後の陣営となった。

![]() 鳥羽・伏見以降の近藤の軌跡が記されている。
鳥羽・伏見以降の近藤の軌跡が記されている。